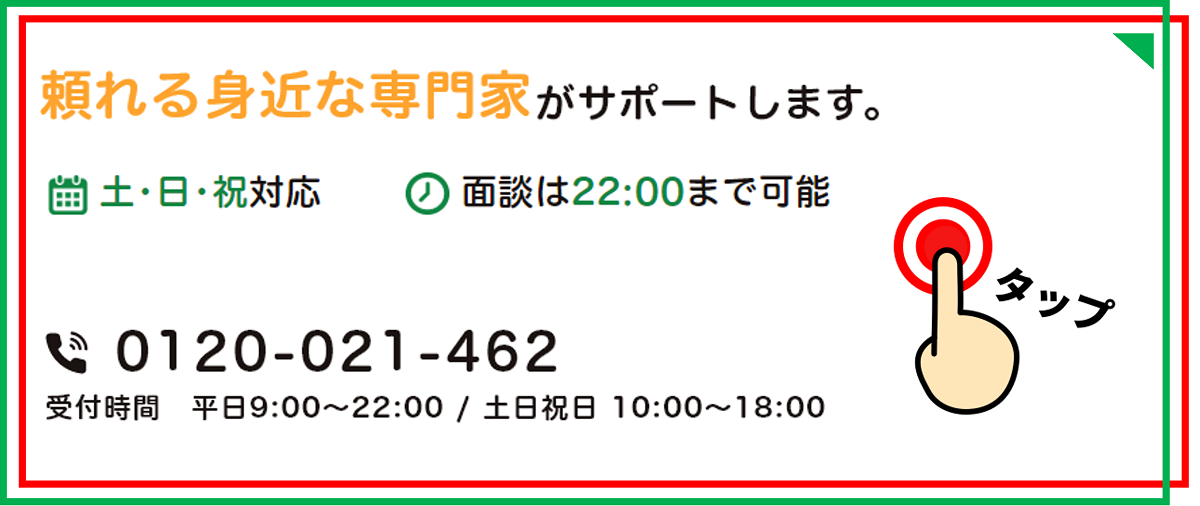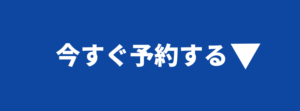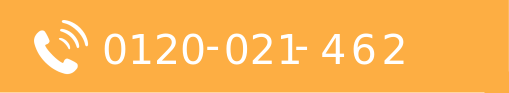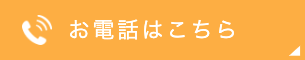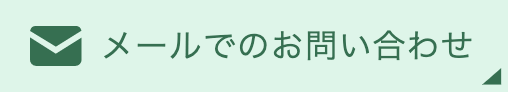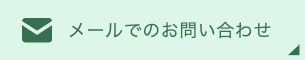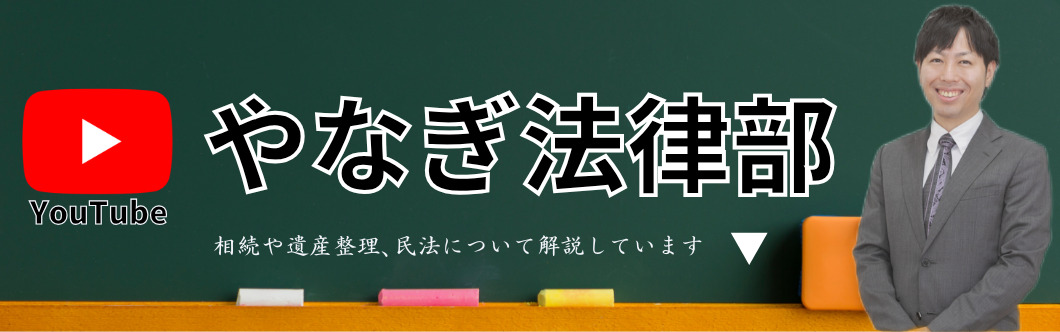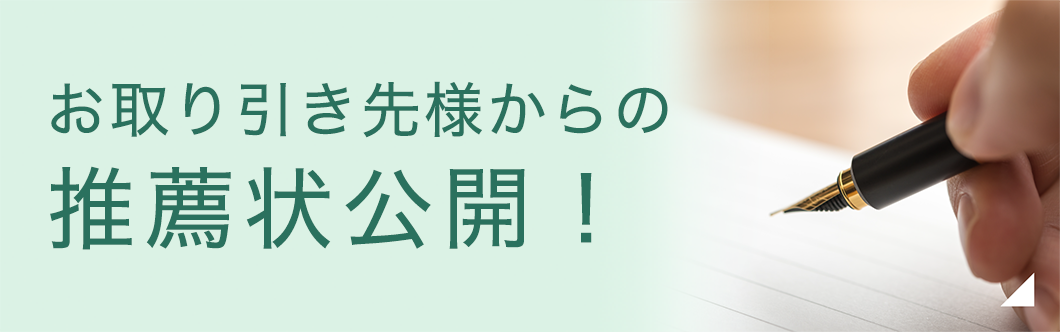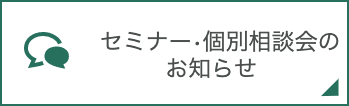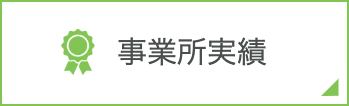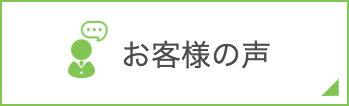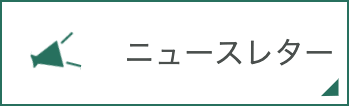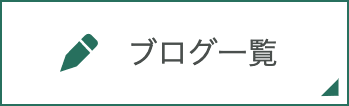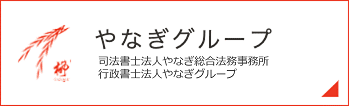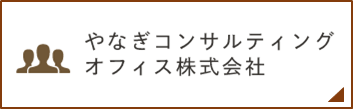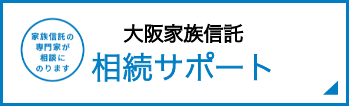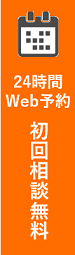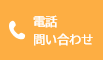解決事例①:相続放棄

目次
亡くなった父の借金が発覚し、相続放棄で解決したケース
ご依頼の状況

T様(42歳・女性、大阪市住吉区在住)は、父親が亡くなってから2か月後、消費者金融から督促状が届いたことで当事務所へ駆け込んで来られました。
T様の父親は、生前は「借金なんてない」と言っていたため、まさか借金があるとは思っていませんでした。
相続人は、T様とお兄様(45歳)、お母様の3人。
父親名義の実家には母親が住み続けており、預金は100万円程度でした。
督促状を見ると、借金の総額は約500万円。
さらに別の金融機関からも督促が来る可能性があり、T様は「このままでは母の生活も守れない」と途方に暮れていました。
相続放棄の期限まで残り1か月を切っており、一刻も早い対応が必要な状況でした。
相談内容
T様の不安と疑問は次の通りでした。
- 本当に500万円以外に借金はないのか、全容が分からず不安
- 相続放棄をすると実家も失うことになるのか
- 母親だけ相続して、子供たちだけ相続放棄できるのか
- 期限まで1か月しかないが間に合うのか
- 相続放棄の手続きを自分でやるのは難しいのか
- 兄が仕事で忙しく、協力してもらえるか心配
「父が亡くなって悲しみも癒えないうちに、こんな借金問題に直面するなんて。もっと早く相談していれば良かった」と涙を浮かべながら話されました。
当事務所のサポート内容

①緊急性の確認と方針決定
まず相続放棄の期限を正確に計算し、残り28日であることを確認。
全員が相続放棄する方針で進めることを決定しました。
お母様も含めて全員が相続放棄すれば、借金を背負う必要はありません。
②財産調査の実施
信用情報機関への照会を行い、他に借金がないか徹底的に調査。
結果、さらに2社から合計200万円の借金が判明し、総額は約700万円であることが分かりました。
一方、めぼしい資産は実家と預金100万円のみで、明らかに債務超過の状態でした。
③戸籍収集と書類作成
相続放棄申述書の作成に必要な戸籍謄本等を当事務所で代行取得。
T様、お兄様、お母様それぞれの申述書を作成し、借金を知った経緯や相続放棄の理由を明確に記載しました。
④家庭裁判所への提出
作成した書類一式を大阪家庭裁判所へ提出。
お兄様は仕事で来所できなかったため、郵送でのやり取りで対応し、全員分を同時に提出しました。
⑤照会書への対応アドバイス
提出から2週間後、裁判所から照会書が届きました。
当事務所で回答内容をアドバイスし、適切に対応。
その結果、全員の相続放棄が無事に受理されました。
結果
相続放棄が受理されたことで、T様ご家族は700万円の借金から解放されました。
実家は失うことになりましたが、「借金を背負うよりも、母と新しい生活を始める方が良い」と前向きに捉えられるようになりました。
お母様は賃貸住宅へ引っ越し、T様たちのサポートを受けながら新生活をスタート。
「あの時、専門家に相談して本当に良かった。
自分たちだけでは、きっと期限に間に合わなかった」と安堵の表情を見せられました。
金融機関からの督促も完全に止まり、精神的な負担からも解放されたT様ご家族。
今では月に一度、家族で食事をする時間を大切にされているそうです。
本事例のポイント
- 相続放棄の期限3か月は思っている以上に短く、早めの相談が重要
- 借金の全容を把握するには信用情報機関への照会が不可欠
- 相続人全員が同時に手続きすることで、スムーズに進められる
- 実家を失っても、借金から解放される方が家族の将来のためになることも
- 専門家のサポートで、期限内の確実な手続きが可能に
 |  |
| 相続サイト | |
| 所在地 |
|
| その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格