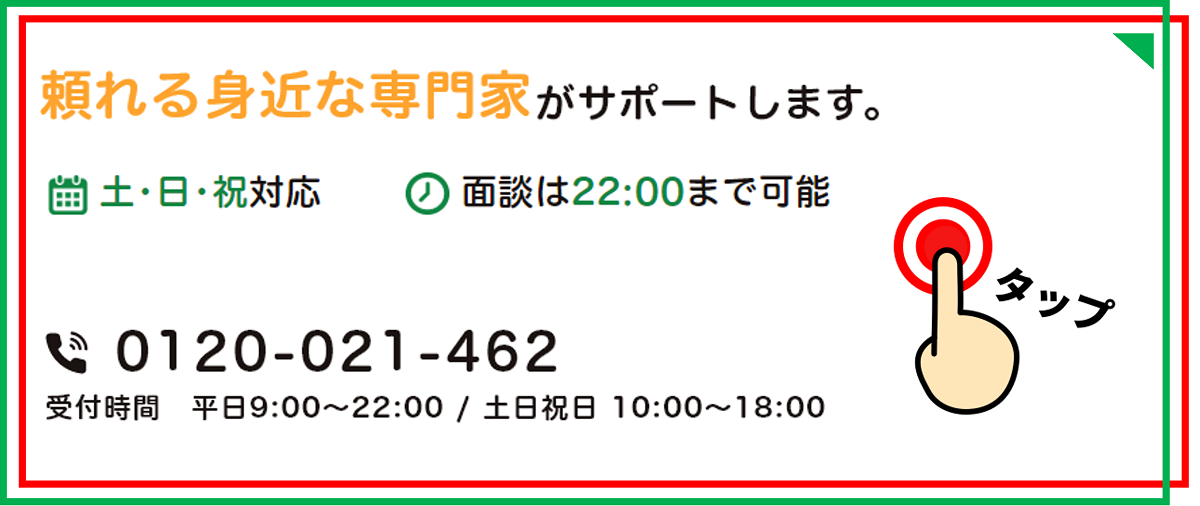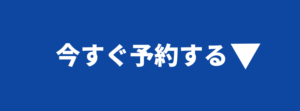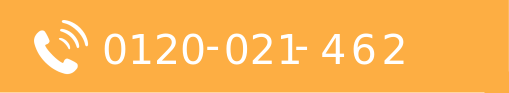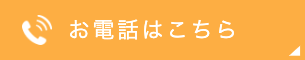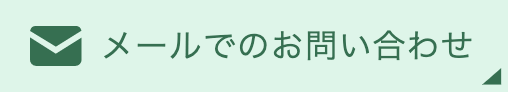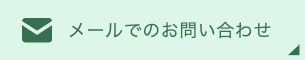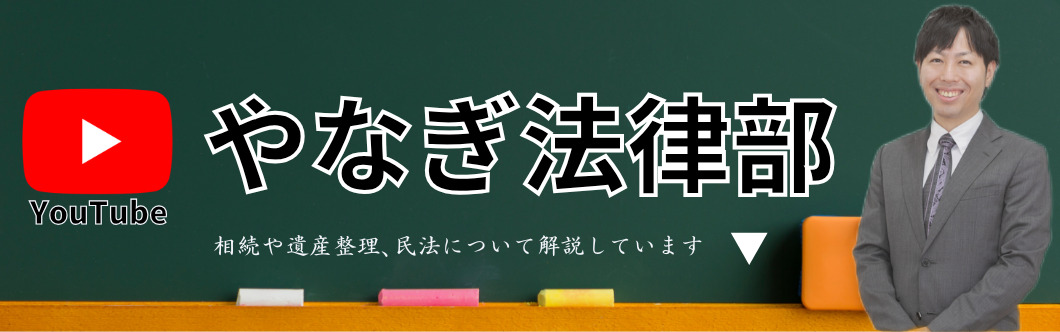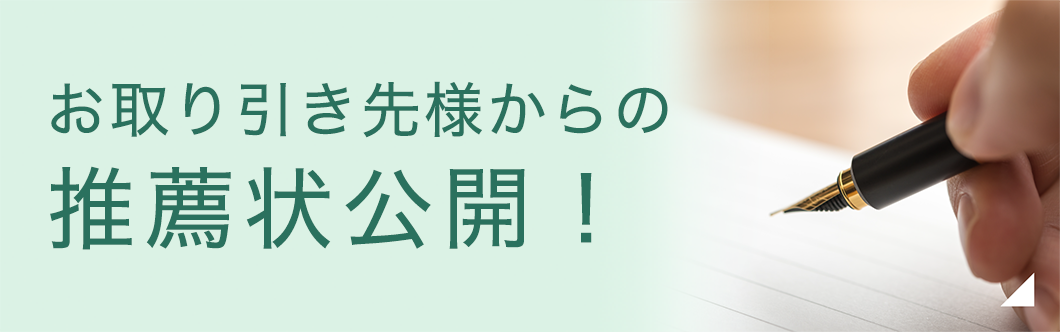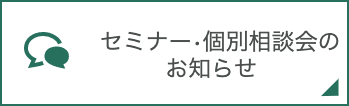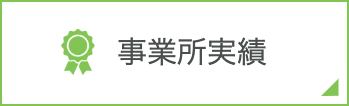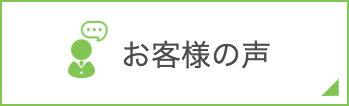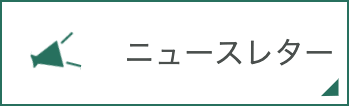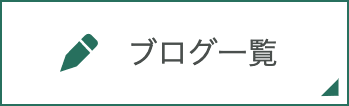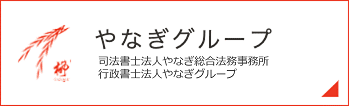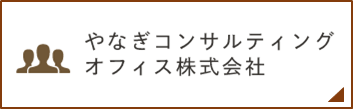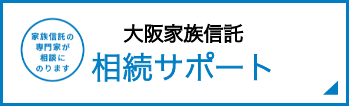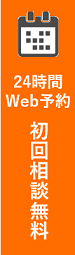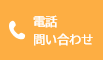解決事例②:遺言書

目次
自筆の遺言書に不備があり、公正証書遺言で作り直したケース
ご依頼の状況

Y様(68歳・女性、大阪市天王寺区在住)は、5年前に自分で作成した遺言書に不安を感じ、当事務所へ相談に来られました。
Y様は3年前に夫を亡くし、相続人となるのは長女(43歳・看護師)と次女(39歳・専業主婦)の2人。
財産は、自宅マンション(評価額約2,500万円)、預貯金約1,500万円、夫から相続した有価証券約500万円でした。
長女は独身でY様の近くに住み、毎週のように様子を見に来てくれています。
一方、次女は結婚して子供が3人おり、年に数回しか会えません。
Y様は「面倒を見てくれている長女に多く残したい」と考え、5年前に自筆で遺言書を書いていましたが、「本当にこれで大丈夫なのか」と不安が募っていました。
相談内容
Y様の心配事は次の通りでした。
- 自筆の遺言書が法的に有効なのか分からない
- 長女に6割、次女に4割という分け方で問題ないか
- 日付を「令和○年○月吉日」と書いてしまったが大丈夫か
- 訂正箇所に二重線を引いただけで、訂正印を押していない
- 預金の記載が「○○銀行の預金」とだけ書いており、口座番号がない
- 次女から遺留分を請求されないか心配
「インターネットを見ながら書いたけれど、これで本当に私の想いが伝わるのか。長女と次女が争うことになったら本末転倒」と不安そうに話されました。
当事務所のサポート内容

①既存の遺言書の確認
Y様が持参された自筆遺言書を確認したところ、残念ながら複数の不備が見つかりました。
特に日付の「吉日」という記載は、特定の日付と認められず無効となる可能性が高いこと、訂正方法も法律の要件を満たしていないことを説明しました。
②財産の正確な調査
現在の財産状況を正確に把握するため、不動産の登記簿、預貯金の残高、有価証券の評価額を調査。
5年前から財産内容が変わっている部分も確認し、最新の財産目録を作成しました。
③遺留分に配慮した内容の検討
次女の遺留分(4分の1)を計算し、Y様の希望である「長女6割、次女4割」でも遺留分を侵害しないことを確認。
さらに、なぜこのような分配にしたのか、付言事項に記載することをご提案しました。
④公正証書遺言の作成準備
必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書、固定資産税評価証明書など)を当事務所で代行取得。
Y様の想いを丁寧にヒアリングし、法的に確実な遺言案を作成しました。
⑤公証役場での遺言作成
公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場で公正証書遺言を作成。
当事務所スタッフ2名が証人として立会い、無事に完成しました。費用は約8万円でした。
結果
公正証書遺言が完成し、Y様は「これで安心して老後を過ごせる」と胸をなでおろされました。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
その後、Y様は長女と次女を呼んで、遺言書を作成したことと、その内容を伝えました。
付言事項には「長女には日頃の世話に感謝している。次女には3人の子供たちの教育費に使ってほしい」という想いを記載。
両姉妹とも「お母さんの気持ちがよく分かった」と納得されました。
「自筆の遺言書のままだったら、きっと無効になって姉妹でもめていたかもしれない。
専門家に相談して本当に良かった」と、Y様は安堵の表情を見せられました。
本事例のポイント
- 自筆証書遺言は約7割に何らかの不備があるため、専門家のチェックが重要
- 日付の「吉日」記載や、訂正方法の誤りは致命的な不備となる
- 公正証書遺言なら形式不備の心配がなく、確実に想いを残せる
- 遺留分に配慮し、付言事項で理由を説明することで、相続人の納得を得やすい
- 遺言の内容を生前に伝えることで、相続発生後のトラブルを防げる
 |  |
| 相続サイト | |
| 所在地 |
|
| その他 |
|
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格