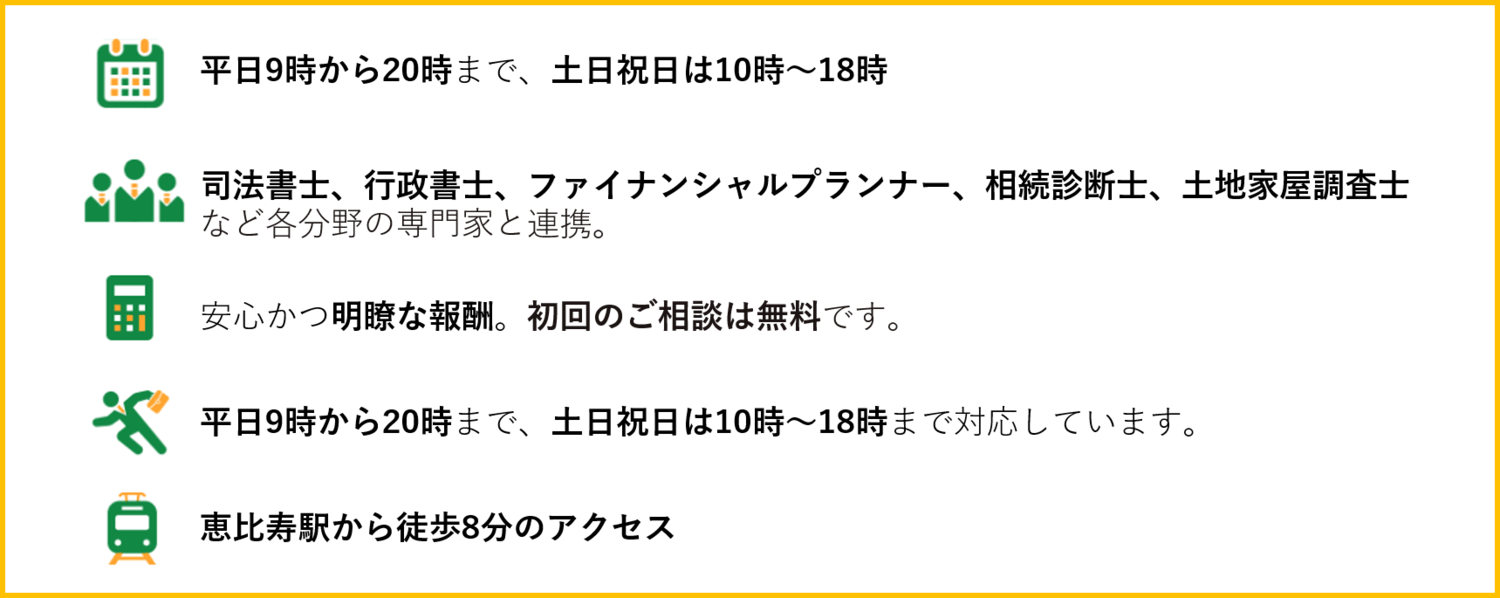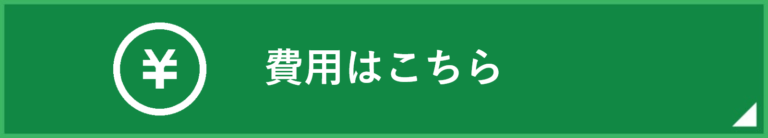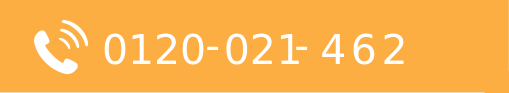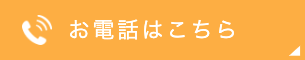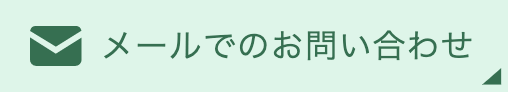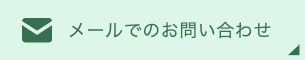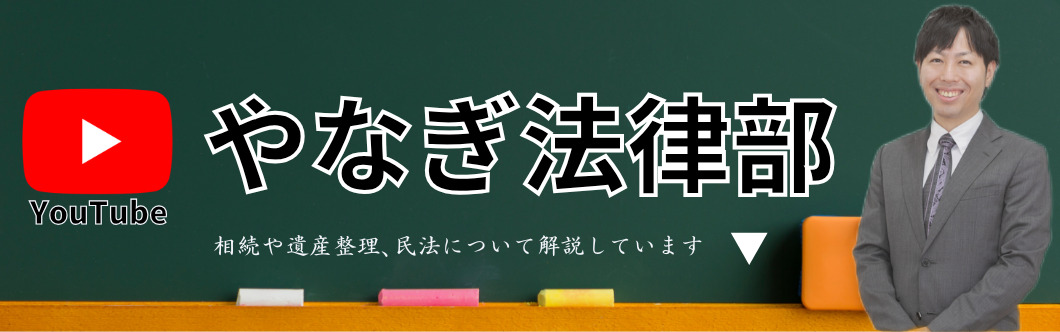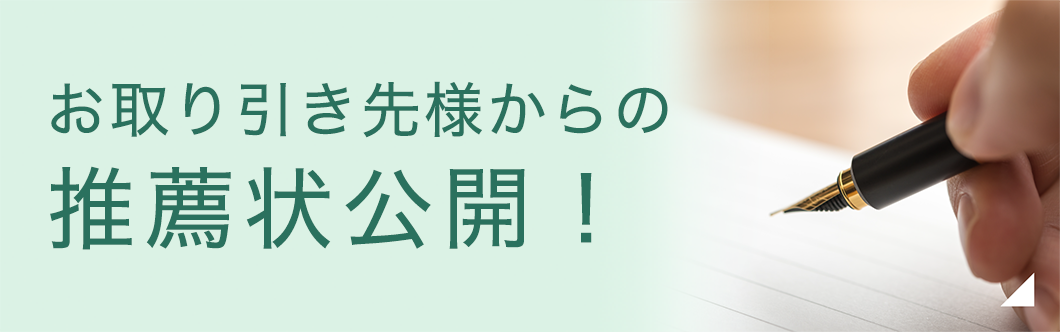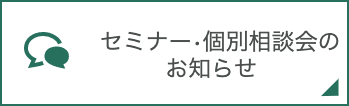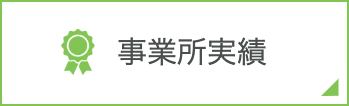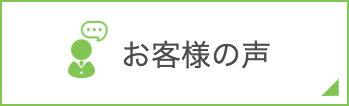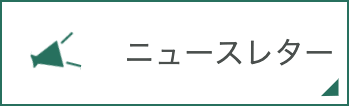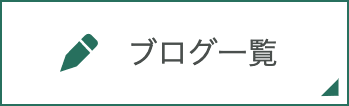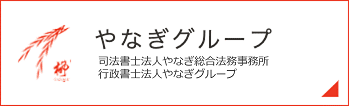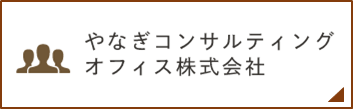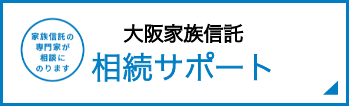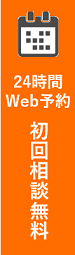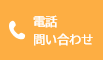相続放棄 の関連記事
- 2024/08/19
- 住宅ローンの相続対策
- 2024/05/03
- 空き家を持っているけどどうすればいい?空き家問題の解決と処分方法
- 2024/04/19
- 役所からの突然の手紙、いつの間にか相続人になっていた
- 2023/12/06
- 相続放棄したのに財産を処分してしまった!? 無効になるケースと対処法まとめ
- 2023/03/02
- 相続放棄しても「管理責任」を負わなければならない?!
- 2023/02/02
- 兄弟間での相続放棄ってどうやるの?どうなるの?疑問を一気に解決。
- 2022/08/03
- 相続放棄の失敗例を解説