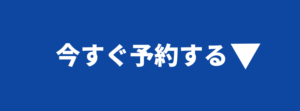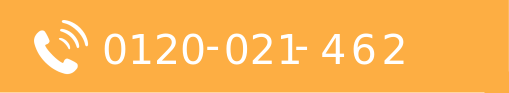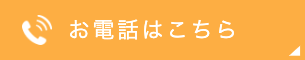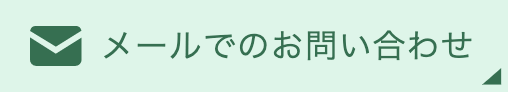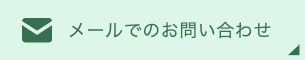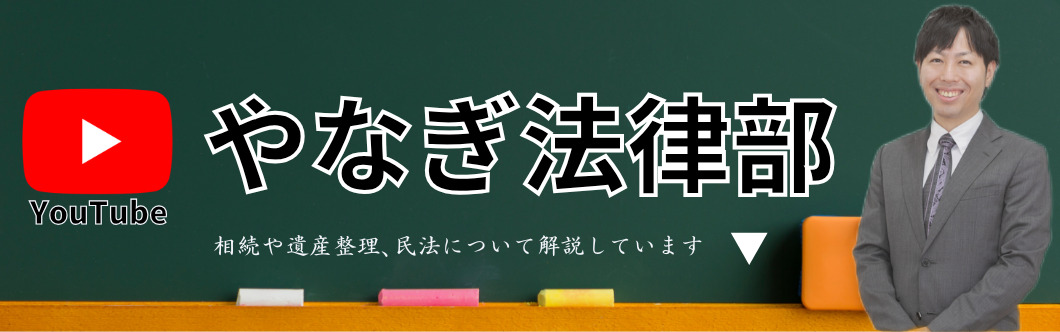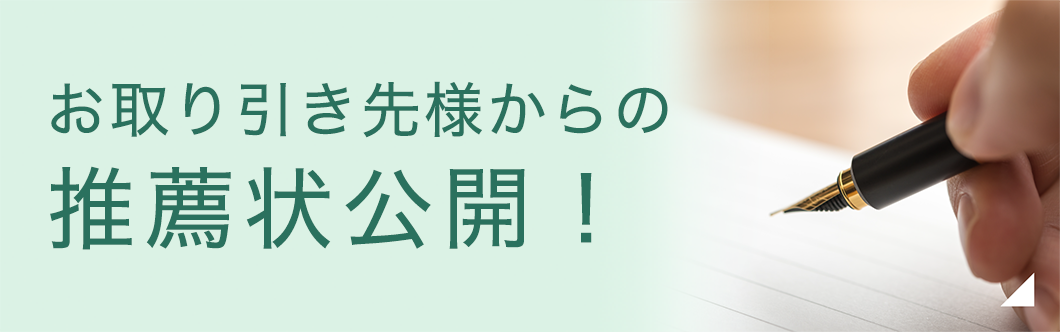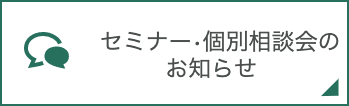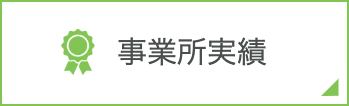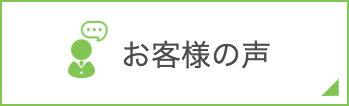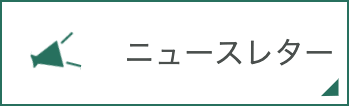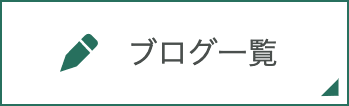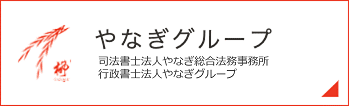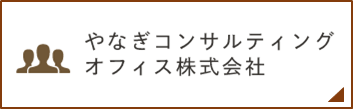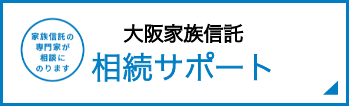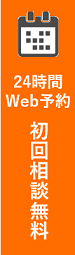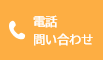生前贈与で「現金手渡し」はできるのか!?

生前贈与はすぐにでも始められる相続税対策ですが、一定額を超えると贈与税がかかってしまいます。
そこで、現金手渡しの生前贈与は痕跡が残らないため、贈与税を払わずに財産移転できると考える方もいらっしゃいます。
しかし、そうした場合注意しなければいけません。
今回は生前贈与で現金を手渡しした場合どうなるのかについて解説していきます。
相続税対策や生前贈与を検討中の方は参考にしていただけると幸いです。
目次
- 生前贈与とは
- 生前贈与とは
- 生前贈与をするメリット
- 「現金手渡し」で生前贈与するとどうなるのか
- 税務署から指摘される
- 暦年贈与として認められない可能性
- 「現金手渡し」で生前贈与するときの注意点
- 贈与契約書の作成
- “贈与の都度”作成する
- 相続開始前3年以内の贈与
- まとめ
生前贈与とは
まず始めに生前贈与について説明していきたいと思います。
生前贈与とは
金銭や不動産などの財産を自分が存命のうちに贈与することを生前贈与といいます。
贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)両方の意思表示が必要で、贈与者が一方的に財産をあげたとしても、受贈者が受け取ることを承諾していない場合、贈与は成立しません。
両者の「あげる」「もらう」の意思表示が必要です。
子や孫名義の口座を作って積み立てる「名義預金」の場合、
親が一方的に子や孫の口座を作って積み立てていると、税務署から家族の名義を借りているだけの「名義預金」と見なされ、結局、親の財産として相続税の対象になることがあります。生前贈与をするメリット
生前に贈与をすることで死後の遺産を減らすことができるため、相続税がかかる人の場合相続税の軽減効果があります。
また、生前贈与で財産をもらった人にかかる贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
1年間に110万円以下の金額の贈与であれば贈与税がかかりません。この制度を利用した贈与のことを暦年贈与と呼びます。
自分の財産を贈与する相手や時期を自由に決められることもメリットと言えるでしょう。
相続人同士のトラブルを防げたり、これから価値が上昇する可能性の高い株式を、まだ非常に安値であるうちに贈与することで、節税効果を得ることができるでしょう。
贈与税の速算表
速算表の利用に当たっては基礎控除額の110万円を差し引いた後の金額を当てはめて計算してください。それにより贈与税額が分かります。<一般贈与財産用>
兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など基礎控除後の課税価格 200万円
以下300万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下3,000万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 <特例贈与財産用>
祖父から孫への贈与、父から子への贈与など基礎控除後の課税価格 200万円
以下400万円
以下600万円
以下1,000万円
以下1,500万円
以下3,000万円
以下4,500万円
以下4,500万円
超税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 控除額 ‐ 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm「現金手渡し」で生前贈与するとどうなるのか
生前贈与の主な目的は相続財産を減らすことなので、贈与が認められなければ相続税対策にはなりません。
贈与の事実が分かるようなものを残しておく必要があるのですが、証拠が残りにくい現金手渡しは贈与方法としておすすめできません。
税務署から指摘される
現金手渡しだと、銀行などの第三者を介さずにやり取りをするので、記録に残らず、お金のやり取りは外から分からないと思われるかもしれません。
しかし、実際には生前贈与を税務署に隠し通すことは難しいでしょう。
税務職員は、周辺の事実を総合的に調査し、贈与の事実にたどり着くことができるからです。
税務署は、税務調査の名目で銀行口座を調べる権限があるため、受贈者が自分名義の口座に入金すると「お金の出どころはどこか?」と問われることになってしまいます。
贈与者の出金日や出金額、使い道の調査をされ、最終的には現金手渡しが露呈します。贈与税は、期限内に申告をしなければ、本税に加えて追徴税が課せられる可能性があります。
また、年間110万円までの贈与は非課税になりますが、110万円以上の贈与を意図的に申告しなかった場合は重加算税が課される可能性もあります。暦年贈与として認められない可能性
税務調査の結果、「資金が移動しているものの、生前贈与ではない」という判断になる可能性もあります。
贈与は、贈与者と受贈者の同意があって成立するので、この同意がなかったと判断されれば、
110万円以下の贈与であっても相続財産にカウントされるため、相続財産を減らせず、相続税が高額になる可能性があります。「現金手渡し」で生前贈与するときの注意点
以上のように、現金手渡しで生前贈与を行うと節税の目的を達成できない可能性がありますので、次の3点に気を付けてみて下さい。
贈与契約書の作成
現金手渡しであっても、贈与を行う場合には「贈与契約書」を作成するようにしましょう。
これにより、税務署に生前贈与があったことの説明や証明がしやすくなります。
贈与契約書の作成は、弁護士などの専門家に依頼することもできますが、自分で作成しても問題はありません。<贈与契約書サンプル>
贈与契約書
贈与者 (以下、「甲」という)と受贈者 (以下、「乙」という)は、以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 甲は、乙に対して、その所有する現金〇〇万円を贈与することを約し、乙はこれを承諾した。
第2条 甲は、第1条に基づき贈与した現金を、令和〇年〇月〇日までに、乙が管理する下記の預金口座に振り込む方法により贈与することとする。
〇〇銀行〇〇支店(普通預金口座/口座番号〇〇)
以上の契約を証するため本契約書2通を作成し、甲乙は署名押印し、各1通を保有する。
以上
令和〇年〇月〇日
贈与者(甲)
住所
氏名 ㊞
受贈者(乙)
住所
氏名 ㊞
“贈与の都度”作成する
例えば、10年間にわたり毎年100万円の贈与を行う場合において、「100万円の贈与契約を10年連続で交わした場合」と「毎年100万円を10年間にわたり贈与する契約を交わした場合」とでは、税務上の取り扱いが変わります。
暦年贈与を利用したい場合には、「100万円の贈与契約を10年連続で交わした場合」となりますので、毎回贈与契約書を作成しておきましょう。
「毎年100万円を10年間にわたり贈与する契約を交わした場合」には、定期贈与と判断され、暦年贈与とはみなされませんので要注意です。
定期贈与と判断された場合、1,000万円の贈与がなされたとみなされ、贈与税を支払わなければなりません。※定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与するとあらかじめ決めたうえでおこなわれる贈与のことです。
相続開始前3年以内の贈与
贈与者の死亡からさかのぼって3年以内の贈与については、贈与ではなく相続であるとみなされ相続税の課税対象になります。(2024年からは死亡からさかのぼって7年以内の贈与に延長されることになりましたのでご注意ください。)
これは、死期が迫った人の財産を慌てて移転させるなど、相続税逃れを防止するための措置です。この場合、この期間内の贈与については贈与税の基礎控除は受けられませんので、注意が必要です。
もっとも、相続税の基礎控除は、贈与税の基礎控除よりも多いので、相続とみなされたとしても相続税を支払わなくてよいケースも考えられます。
まとめ
今回のお話をまとめると以下のようになります。
生前贈与とは ・両者の「あげる」「もらう」の意思表示が必要 ・相続税の軽減効果がある(年間110万円の基礎控除を利用する)
・贈与する相手や時期を自由に決められる
現金手渡しで生前贈与するとどうなるのか ・税務署から指摘され、追徴税が課せられる可能性、重加算税が課される可能性がある ・暦年贈与として認められない可能性がある
現金手渡しで生前贈与するときの注意点 ・贈与契約書の作成をする ・“贈与の都度”作成する
・相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税対象となる(2024年からは7年以内)
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「無料相談」のご予約は下記の「空き状況検索」からできます。是非ご活用ください。
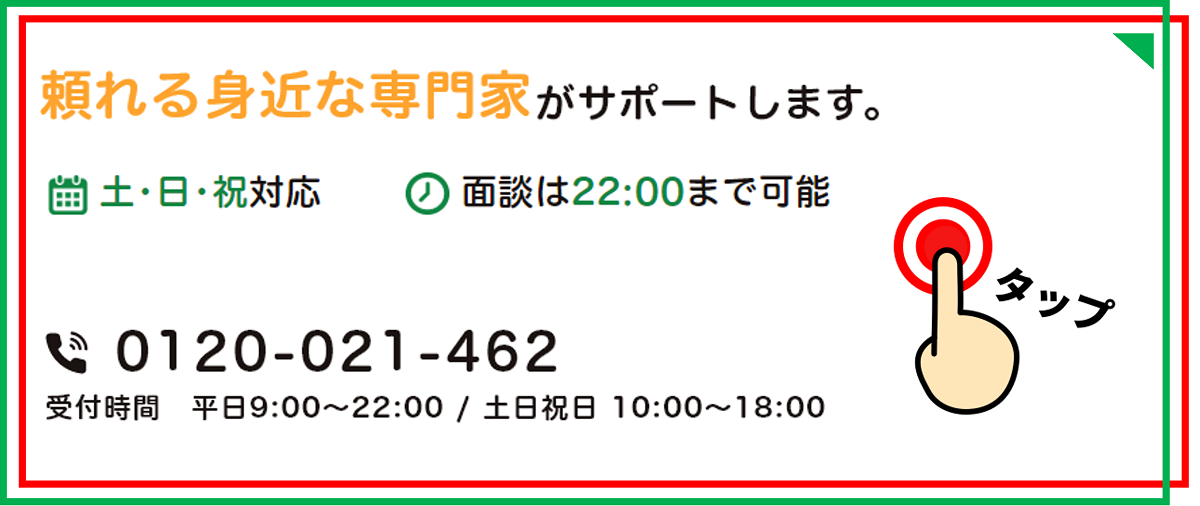


相続サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号 あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
その他 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
著者情報
代表 柳本 良太

- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格
司法書士法人やなぎ総合法務事務所運営の相続・家族信託相談所